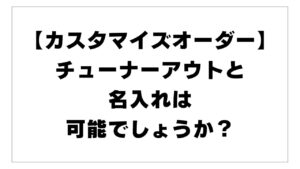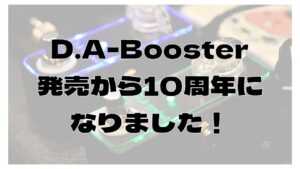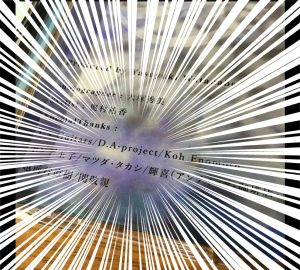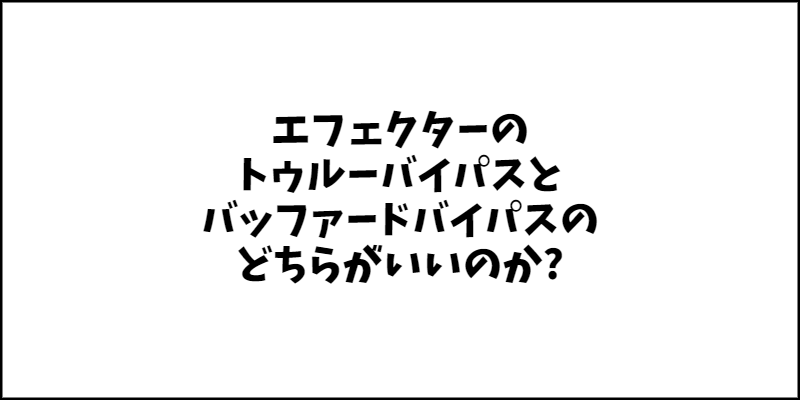
D.A-Boosterを注文する時に
トゥルーバイパスとバッファードバイパスのどちらがいいか?
という質問をたまにいただきますので、そういった疑問をもたれる方のために、作っている側としての選び方を書いておきます。
エフェクターのインピーダンスとバッファーのかんたんなお話
まず最初に「インピーダンス」について理解しておくととても分かりやすいかと思うので簡単に説明します。
インピーダンスのお話は難しいと思う方もいると思いますが、これだけ覚えておけばいいと思います。
- ハイインピーダンスはノイズの影響を受けやすい
- ローインピーダンスはノイズの影響を受けにくい
これだけなので簡単だと思います。
じゃあ、実際にドコまでがハイインピーダンスになっているか?ですが、
エフェクターを繋いでいる場合はそのエフェクターがトゥルーバイパスじゃない場合、例えばBOSSの歪エフェクターなどの場合はその中でローインピーダンスに変換されます。
この変換をするのがバッファーです。
このバッファーを通ったあとはローインピーダンスになるのでノイズの影響を受けにくくなります。
なので、パッシブピックアップを使っている場合は出来るだけ、ギターから近いところでローインピーダンスにしてあげるとノイズの影響を受けにくいシステムにできます。
そのために質のいいバッファーが大事ということです。
エフェクターはローインピーダンスに変換するバッファーとして使いたい場合はバッファードバイパス、ブーストとして使うならトゥルーバイパスがいい。
ここからが本題となります。
D.A-Boosterをギター直後に入れた場合に、トゥルーバイパス・バッファードバイパスによる違いが大きく影響します。
※ギターのピックアップがパッシブの場合です。
トゥルーバイパスの場合、D.A-Boosterをオフにした時にはD.A-Booster回路を通らないので、ギターからの信号はノイズの影響を受けやすいハイインピーダンスのまま出力されます。
バッファードバイパスの場合は、D.A-BoosterをオフにしたときもD.A-Booster回路を通り、ハイインピーダンスの信号をノイズの影響を受けにくいローインピーダンスにして出力します。
そのために、D.A-Boosterをローインピーダンスに変換するバッファーとして使いたい場合はバッファードバイパス仕様がいいです。
他のエフェクターをバッファーとして使い、D.A-Boosterはブーストとして使うならトゥルーバイパスでいいと思います。
2つのバッファーとブースターとしてD.A-Boosterを使用するという方もいます。
また、このことからギター直後にバッファーとしてD.A-Boosterバッファードバイパスを入れて、歪み系エフェクターの後や、マスターボリュームとしてD.A-Boosterトゥルーバイパスを入れるといった。2つのD.A-Boosterで挟んで使われている方もいらっしゃいます。
またこの時に、2つ分のスペースと電源が必要になるので、自分のシステムに合ったD.A-Boosterを求めてカスタマイズオーダーをいただくこともあります。
使われるギターシステムに合わせてD.A-Boosterを選んでいただければと思います。